公益財団法人川喜多記念映画文化財団
千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル
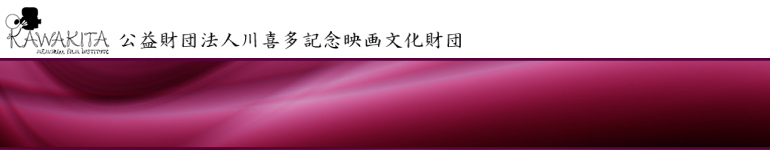
映画祭レポート
◇ベルリン国際映画祭 2025/2/13-23
Internationale Filmfestspiele Berlin








| **受賞結果** | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金熊賞 | Dreams(Sex Love) Dag Johan Haugerud | |||
| 銀熊賞 | 審査員大賞 | The Blue Trail Gabriel Mascaro | ||
| 審査員賞 | The Message Ivan Fund | |||
| 最優秀監督賞 | Huo Meng (for ‘Living the Land’) | |||
| 最優秀主演俳優賞 | Rose Byrne(in ‘If I had Legs I’d Kick You) | |||
| 最優秀助演俳優賞 | Andrew Scott (in ‘Blue Moon ’) | |||
| 最優秀脚本賞 | Radu Jude (for ‘Kontinental ‘25’) | |||
| 芸術貢献賞 | The Ice Tower Lucile Hadzihalilovic | |||
| 最優秀新人作品賞 | The Devil Smokes(and Saves the Burnt Matches in the Same Box) Ernesto Martinez Bucio |
|||
| 短編部門 | 金熊賞 | Lloyd Wong,Unfinished Lesley Loksi Lan | ||
| 銀熊賞 | 普通の生活 水尻自子 | |||
| ジェネレーション部門Kplus | 金熊賞 | The Botanist Jing Yi | ||
| *Special Mention授与 | 海辺へ行く道 横浜聡子 | |||
| 国際批評家 連盟賞 |
コンペ部門 | Dreams(Sex Love) Dag Johan Haugerud | ||
| パースペクティブズ部門 | Little Trouble Girls Urska Djukic | |||
| パノラマ部門 | Under the Flags, the Sun Juanjo Pereira | |||
| フォーラム部門 | The Memory of Butterflies Tatiana Fuentes Sadowski | |||
|
Berlinale Camera (貢献賞) |
Rainer Rother(Germany) | |||
|
Honorary Golden Bear (金熊名誉賞) |
Tilda Swinton(UK) | |||
**概観**

|
| 雪の残るベルリン映画祭会場周り |
ここ10年ほどの暖冬と大きく異なり、人々がこの時期のベルリンと聞いてイメージするであろう、凍てつく空気や雪にも見舞われた極寒のベルリン映画祭であった。オープニングの夜にはそれなりにまとまった雪が降り、終盤近くまで残り続けた。
映画祭の新ディレクターにトリシア・タトル氏を迎えての初めての回、注目が集まっていた。プログラミングに係わるメンバーも大幅に刷新された。顕著な変化としては、新部門「パースペクティブズ(PERSPECTIVES)」の創設である(昨年まで存在していたエンカウンター部門はなくなった)。新部門は新人監督作品に特化したコンペ部門で、今回は10作品で競われた。そしてレッドカーペットを彩るスターたちの数が一気に増えたことも変化であった。ティモシー・シャラメ、イーサン・ホーク、ロバート・パティンソンなど、主にハリウッドから多くのスターが詰めかけた。前任地・ロンドン映画祭を華やかな一大映画イベントに変化させたタトル氏のネットワークあってのことと考えられる。彼らをひと目見ようとメインゲストが多く宿泊しており、公式記者会見場も設けられているグランドハイアットホテル前には多くのファンが詰めかけていた。

|
| メインホテル裏。スターをひと目見ようと集う人々 |
懸案であるメイン会場、ポツダム広場付近の上映会場の不足問題にも着手した。ベルリン映画祭の会場として、かつてはポツダム広場のソニーセンター内のシネマコンプレックス、シネスター、至近のシネマックス・ベルリンが稼働していたが、前者は全面使用不可となり、後者は改築による席数減のためプレス向け上映などに限定されるようになり、ポツダム広場周辺での上映会場の不足がここ数年問題となっていた。アレクサンダー広場のシネスター・キュービックスをサブ会場的に使用しているが、ポツダム広場やマーケットのメイン会場であるマーティン・グロピウス・バウからは距離があるため、映画祭参加者からは不満の声が上がっていた。そんな中、今回からメイン劇場・ベルリナーレ・パラストの目の前の常設館、ブルーマックス・シアターを期間中は映画祭の会場として使用することになった。500席の会場の追加は大きい。パースペクティブズ部門の作品を上映が主であったが、他部門の作品の上映もあった。尚、市をあげての映画祭であるベルリン映画祭は外国人ゲストにはハードルが高いものの、会場は市内各所に20館以上が点在している。一般の映画館(いわゆるアートハウスが多い)が主であるが、インスタレーション作品も選出されていることから美術館なども使用される。多くのエリアで市民が映画祭にアクセスできる、都市型映画祭としてのひとつのモデルといえる。

|
| 今年から映画祭会場に加わったブルーマックス・シアター |
また映画祭の開催中、ベルリナーレ・パラスト前にフェスティバルのハブとなることを目指した「ベルリナーレ・ハブ75(Berlinale HUB75)」を仮設した。このハブでは、映画祭の参加者向けに一連の無料モーニング座談会やイベントが開催され、業界や映画制作者のゲストのためにネットワーキングスペースも提供された。映画祭参加者はパスを提示することで入場できる。バーのような趣きで有料であるが飲み物・軽食が取れ、内部もきれいで快適ではあったが、15時からのみの開場で待ち合わせ等にはいまひとつ不便、会場の広さも十分とは言い難かった。
映画祭(特にベルリンのような巨大な)を就任一回目から大きく変えることはまず不可能である。今回は改革の緒に就いたところであろう。

|
| 新設された「ベルリナーレ・ハブ75」 |
メインコンペティション部門はアメリカの映画監督、トッド・ヘインズ氏を審査員長とし、7名の審査員による審査員団であった。女性4名・男性3名で構成され、出身地域や性別、年代、多様な要素を鑑みて選出していることがうかがえる。アジアからは中国の俳優、ファン・ビンビン氏が名を連ねていた。他部門の賞の審査員は3名での構成であるが、いずれも女性2名・男性1名で、新部門パースペクティブズに関しては3名すべてが女性であった。日本からはベルリン映画祭とは縁の深い想田和弘監督が、ドキュメンタリー部門の審査員として参加していた。コンペティション部門には19作品が選出された。残念ながら前回に続き、今回も日本からの選出はなかった。金熊賞に輝いたのはノルウェーのダーグ・ヨハン・ハウゲルード監督による『Dreams(Love&Sex)』。同作は、ハウゲルード監督による『Sex, Love, Dreams』3部作の完結編。女子高生が女性教師に抱く恋心を描いたラブストーリーで、会期中から好評を博していた。

|
| ドキュメンタリー部門審査員・想田監督のポートレート
|
映画界への長年の功績を讃える金熊名誉賞は俳優のティルダ・スウィントン氏に授与された。スウィントン氏は2009年にはベルリン映画祭の審査委員長も務めている。約40年にわたるめざましい活動を振り返るにつけ、納得の受賞であろう。ベルリン映画祭の何らかの部門で上映された出演作は26作品にのぼるとのことである。堂々たる受賞スピーチも話題となった。

|
| ライトアップされたメイン劇場、ベルリナーレ・パラスト
|
映画祭併設のヨーロピアン・フィルム・マーケット(EFM)は映画祭と同日に初日を迎え、盛況のうちに19日に閉幕した。ベルリンに限らないことだが、マーケットの最終日はすでに帰路に着いている業者がほとんどで閑散としている。今回はマーケットのメイン会場マーティン・グロピウス・バウの2階に”Innovation Hub"が新たに設置され、AIサービス企業やテックベンチャーと、プロデューサー・マーケターの交流の場となっていた。時代のトレンドに対応してゆく必要が常に求められるマーケット運営である。
ベルリンをはじめ、海外の主だった映画祭は政治的意見表明の場となることも多い。プレスも登壇者の政治的スタンスについて遠慮なく質問を投げかけてくる。今回も審査委員長であるトッド・ヘインズ氏がアメリカを含めた世界状況においての意見を求められていた。日本の国際映画祭で世界情勢への見解を問われる場面には出くわしたことはおそらくない。その違いはなんなのだろう、と考えてしまった。
**日本映画**

|
| 『海辺へ行く道』フォトコール。 横浜聡子監督(左)、原田琥之佑氏(右) |
今回の映画祭への日本作品は本数としてはここ20年くらいの中で最少であった。コンペティションのみならず、スペシャルスクリーニングなど、華やかさで耳目を集める部門にまったく日本作品から選出がないのは本当に珍しい。短編コンペティション部門に水尻自子監督のアニメ『普通の生活』、ジェネレーション部門のなかでも4歳以上を対象とするGeneration Kplusコンペティション部門に横浜聡子監督の『海辺へ行く道』、パノラマ部門に非行少年の再生の難しさを描いた藤原稔三監督の『ミックスモダン』、クラシック部門には増村保造監督作品、『清作の妻』4Kリマスター版が選出された。本数は寂しかったものの、いくつか朗報も聞かれた。水尻監督の『普通の生活』は短編部門の銀熊賞(審査員賞)を受賞、『海辺へ行く道』は国際審査員のスペシャルメンションを受けた。フォーラム部門出品の小田香監督最新作『underground』は、海外の地下に題を取った作品を作り出してきた小田監督が日本の地下世界にカメラを向けた作品。小田監督と主演の吉開奈央氏が登壇、熱い質疑応答が繰り広げられた。『海辺へ行く道』は三好銀氏の最高傑作と名高い漫画作品の映画化。上映中は随所で笑いが起こり、上映後の横浜監督と主演の原田琥之佑氏による質疑応答も終始和やかな雰囲気に包まれていた。クラシック部門には毎年、何らかの日本作品が入っている。近年は特に人気の部門となっており、応募作品もかなり多いとのことであるが、作品の質のみならず日本の修復技術の高さの証左ともいえるだろう。

|
| 『underground』上映後の質疑応答。 小田香監督(右から3人目)、吉開菜央氏(右から3人目) |
日本映画への公的なサポートは年々手厚くなってきている。今回も文化庁の日本映画の海外発展事業の一環として、委託先のユニジャパンを通じて3人の新進監督がベルリン映画祭に派遣された。業界関係者とのネットワーク構築を図るプログラムで、また映画祭・見本市の視察を通し、国際的な映画産業への見識を深め、今後の活動の糧とすることを目的としている。今回は荒木伸二、草場尚也、串田壮史氏の3名であった。出発前に事前講義を行い、マーケット参加中にはワークショップ、ピッチを行ったほか、レセプション・交流会参加、イベント見学など精力的に活動した。また、昨年に続き今回も在ドイツ日本大使館にて日独を中心とした、映画関係者を多数招いたレセプションが行われ、盛会であった。近年は映画祭期間中に発行されている日刊の情報誌(’Screen’,‘Variety’等)に日本特集として紹介記事を出稿するなど、日本映画を海外に多方面からプロモーションする動きも加速している。


